
みなさん、夏休みはいかがお過ごしでしょうか。
以前のブログで、「夏休みが始まる前に基礎固めを終わらせよう」と伝えましたが、皆さんはどうだったでしょうか?
計画通りに進んだ人もいれば、思ったように進まなかった人もいるかもしれません。
でも大丈夫です。夏休み後半、あるいは秋からでも「やるべきこと」を明確にすれば、逆転は十分可能です。
そして今こそ取り組んでほしいのが、「個別試験(2次試験)の過去問演習」です。
過去問は、単なる演習問題ではありません。
志望校合格に向けた、もっとも具体的で実戦的な学習ツールです。
「過去問」は大学からのメッセージ
個別試験は大学が独自に作成する試験であり、その大学・学部が「どんな学生を求めているのか」が問題に表れます。
つまり、過去問を解くことは、その大学の「入試のクセ」や「求める力」を知ることなのです。
たとえば、
・英語:長文読解が重視されるのか、文法や英作文に比重があるのか?
・数学:誘導が丁寧な思考型問題か、突き放すような難問が出るか?
・国語:現代文・古文・漢文のバランスや、記述のレベルは?
これらは、過去問を解かなければ絶対に見えてこない情報です。
模試や市販の問題集だけでは、志望校の「空気感」や「出題意図」には気づけません。
過去問は、大学からあなたへのメッセージなのです。
今こそ「本物」に触れるべきタイミング
過去問演習を始めるタイミングとして、夏休み後半から秋にかけてがベストです。
これは、基礎力がある程度ついてきている時期であり、「得点できるか」を意識した勉強にシフトすべき段階だからです。
過去問を解くことで得られるものは次のようなものがあります。
・実際の試験時間でどれだけ解けるか(時間配分の感覚)
・得点につながる解答の仕方(記述の仕上げ方)
・自分の「穴(未習・未理解の部分)」を知ること
・合格に必要な得点ラインとの差分を把握すること
答えを間違えても全く構いません!
むしろ、「どこでつまずくか」こそが最大のヒントです。
現時点での実力を客観的に把握することで、残りの学習計画にリアルな指針を立てることができます。
過去問の「やりっぱなし」を防ぐ3つの工夫
過去問は「解いて終わり」では意味がありません。
むしろ、解いた後の分析・復習こそが最も重要です。
以下の3つの工夫を意識しましょう。
① 解いた直後に自己採点・答案分析
・記述式は、模範解答と比べてどこがズレていたかをチェックする
・「合っていたけど、偶然できた」部分も印をつけておく
② 解き直しは1回で終わらせない
・解説を読んで理解したあとに、数日後にもう一度同じ問題を解いてみる
・何度か解く中で「本当に身についたか」を確認することが大切
③ 過去問ノート・記録表を作成する
・出題分野、配点、正答率、コメントなどを記録して「傾向表」を作る
・年度ごと・教科ごとに並べておけば、復習や特定の大学の作戦立てに役立つ
可能であれば、学校や塾の先生に記述解答を見てもらうのもおすすめです。
自分では気づけない表現のクセや減点ポイントを教えてもらえることで、得点力が格段に上がります。
過去問を解こう!
過去問は、「今の自分の実力を知る鏡」であり、「これからの学習を導く羅針盤」です。
点数に一喜一憂するのではなく、「どうすれば取れるようになるか」を常に意識しましょう。
個別試験の過去問を解くことで、入試本番の空気を“肌で感じる”ことができ、秋以降の勉強がより実践的になります。
志望校合格は、ただ頑張るだけでは届きません。
狙って、届く場所にしていくことが大切です。
今この時期に、過去問という「本物」に向き合いましょう。

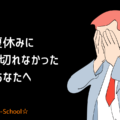
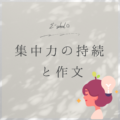

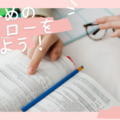


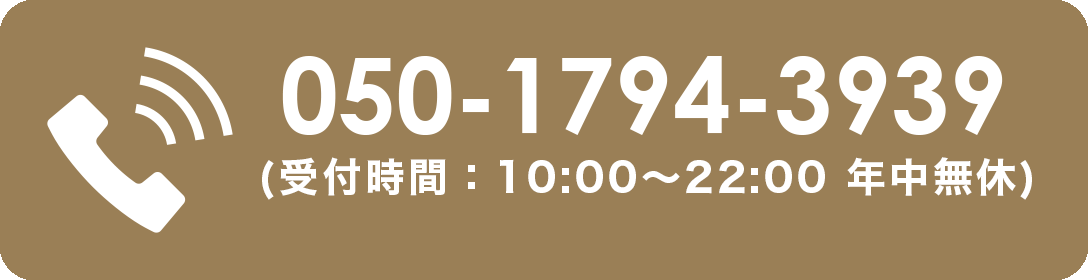

最近のコメント