
9月といえば「お月見」。
日本では昔から、秋の夜に月をながめる習慣があります。
特に「中秋の名月」と呼ばれる夜は、まん丸のお月さまを家族で楽しむ特別な日です。
実は、このお月見は 旧暦の9月(今の暦でいうとだいたい9月中旬〜10月はじめごろ) に行われていた行事で、
ちょうど秋の真ん中に見える美しい月を愛でるものでした。
昔の人たちは月を見て、豊作や健康を祈ったといわれています。
でも、どうしてこの時期の月は特にきれいに見えるのでしょうか?
今回は「月とお月見の科学」を解説していきます。
月が形を変えるしくみ
毎晩のように夜空に浮かぶ月は、毎日すこしずつ形を変えています。
細長い三日月の日もあれば、半分だけ光る半月の日もあり、やがて丸い満月へと変わっていきます。
この不思議はどうして起こるのでしょう?
月は自分で光っているわけではなく、太陽の光を反射して輝いています。
地球が太陽のまわりを回るように、月も地球のまわりを回っています。
そのため、太陽の光が月に当たる角度や位置が毎日すこしずつ変わり、私たちから見える部分が違って見えるのです。
これを「月の満ち欠け(みちかけ)」と呼びます。
お月見のころはちょうど「満月」に近いタイミングで、まん丸の月が夜空にのぼります。
秋の月が特にきれいに見える理由
では、なぜ秋の月はとくに美しいと感じられるのでしょうか?
その理由は「空気」と「高さ」にあります。
まず、秋は空気が乾燥していて、夏のように湿気や水蒸気が多くありません。
空にちりや水分が少ないと光が散らばらず、月の光がくっきりと届きます。
だから秋の月はシャープで明るく見えるのです。
さらに、秋の月はちょうど地平線から昇ってくる時間が早く、夜のあいだ長く観察できます。
しかも、見上げやすい高さにあるので、月がいちばんきれいに見えるのです。
昔の人が「秋は月の季節」と呼んだのも、この科学的な理由があるからなのです。
月の科学と観察のすすめ
月を観察すると、模様が見えることに気づくでしょう。
うさぎがおもちをついているように見えるあの模様は、
実は「クレーター」と「月の海」と呼ばれる地形の組み合わせです。
クレーターは小惑星がぶつかったあとで、黒っぽい「海」はマグマが固まった場所なのです。
望遠鏡や双眼鏡を使うと、もっと細かい地形まで観察できます。
また、月は地球の海にも影響を与えています。潮の満ち引きは月の引力によるものです。
海の水を引っ張る力があるなんて、月はとても不思議な存在ですね。
お月見の夜には、家族で団子を食べながら「今日はどんな形に見える?」「クレーターはどこ?」と観察してみると、
いつもより月がもっと楽しく感じられるはずです。
まとめ
お月見は、ただ美しい月をながめるだけでなく、自然と科学のふしぎを感じられる行事です。
月の満ち欠けや空気の透明さ、地球と宇宙のつながりに気づくチャンスでもあります。
今年のお月見は、団子を食べながら「科学の目」で月を見てみましょう。
きっと、夜空がこれまで以上にワクワクする世界に見えるはずです。
科学は意外と身近なところに潜んでいます。
日常生活で起こるさまざまなことに興味・関心や疑問を持ち、
それを日々の学習につなげることが出来れば勉強はもっと楽しいものになると思います!
E-School☆では、勉強に対する悩みを抱えた生徒さん1人1人に寄り添ってサポートをしています。
勉強を教えることはもちろん、生徒さん自身がやる気、モチベーションを高めるためのお手伝いをすることも、E-School☆の役目です!!少しでも悩んでいることがあれば、メッセージなどでお気軽に相談してくださいね!



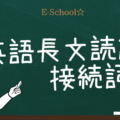



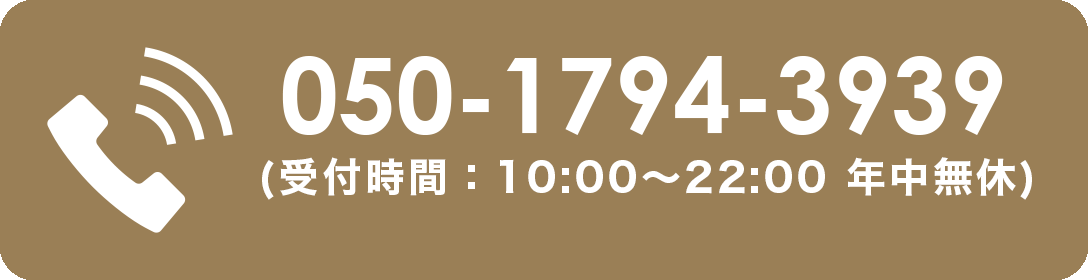

最近のコメント